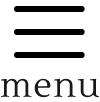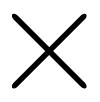当ルームのカウンセリング
2020/03/03
恥トラウマからの癒やし

「自分はダメだ」
「みっともない」
「恥ずかしい」
そんな風に感じられたことは
ありますか?
「人を頼ったり、
依頼するのが怖い」
「だから頼らずに済むように
自分独りで何でも
できないといけない」
「他人と比べ、どうして自分は
こんなにダメなのか
考えてしまう」
「自分じゃない人になりたい」
そんな風に感じたことは
ありませんか?
私たちは人生の中で時に
自己の存在をおとしめられ
辱められ
蔑ろにされ
嘲笑される体験に
曝されることがあります。
そういった状況にあっても
助けが得られず
誤解され
孤独が続くこともあります。
こういった体験は、
あなたが悪くないにも関わらず
あなた自身を、
無価値で
みっともない
恥ずかしいものと感じさせ
自分自身を責め苛ませます。
そして人生の中で新たな危機や
トラブルや傷つきが訪れる度に
「やっぱり自分はダメなんだ」
と繰り返し思わせます。
そして
病巣が広がっていくように、
自己否定感が増していきます。
場合によっては、
自分や他者に怒りを抱えている
かもしれません。
あるいは、
怒ることすら出来ない状態
かもしれません。
あるいは
同じ傷つきを繰り返さないように
「優等生」の仮面や
「良い人」の仮面
を身につけて
生き延びてきた方も
いらっしゃるでしょう。
自分が悪くないにも関わらず
自分が悪いと思わされる...
こんな傷つき体験を
恥トラウマと呼んでみたい
と思います。
これまで考え方を変えようと
努力を重ねられてきた方も
おられると思いますが、
自分個人の力だけで
変えていくのが
難しいのは、
自分が悪いという視点から、
自分の力だけで脱却することが
難しいためです。
しかし
傷つきについて他者に話すのは
勇気がいることです。
当ルームでは、
無理にかさぶたを剥がすような
カウンセリングは
行いません。
恥トラウマからの癒やしには
適切で安全な治療プロセスが
欠かせないためです。
話すことに抵抗がある場合
カウンセラーとの関係に
信頼が持てるまで、
比較的抵抗の少ない相談から
始めるのも良いと思います。
話さなければいけないわけでも
ありません。
私たちは、
自分の内に留めておきたいこと
を話さずにいる権利を
持っています。
別の相談をなさる場合でも、
自分への信頼を取り戻すことで
恥トラウマへの癒やしに
繋がっています。
2019/11/25
承認と愛と依存のこころ

当ルームには、人に依存して苦しくなってしまうという方や人からどう思われるか気にしてしまう
という方がご相談にいらっしゃいます。
しかし、他者から承認を得られると安心できたり、他者に愛されると自信を持てるのは、人間としてごく自然な感情でもあります。
人を好きになっても相手が応えてくれないと苦しみますし、上司や同僚の評価がないと、自分の仕事に手応えを持つことが出来ません。
人間は本能的に他者からの承認と愛を求める生き物です。
人間は他者から承認や愛を得ることで、居場所を見つけられます。
居場所が見つかると自己肯定感が生まれます。
しかし、他者は何を考えているのでしょうか?
人間は他者の承認と愛を求めるように本能的に運命づけられた生き物ですが、他者の気持ちは自分には、コントロールできません。
心理学者コフートはこのような人間の本質を「悲劇の人」と表現しました。
私たちは、得られるかどうか不確かな他者からの承認や愛を求めて焦がれ、時に得られずに傷つくことになります。
そして
「人を頼ってはいけない」
「助けを求めても誰も助けてくれないだろう」
「誰も頼らず一人で何でもできないといけない」
といった信念が刻み込まれ、サポートを得られず、困りやすかったり、孤独な気持ちで過ごされる方もいます。
また、こういった苦しみを紛らわすために、占いや買い物、アルコール、ゲームなどさまざまな依存に走る方もいらっしゃいます(「ハマりすぎなのでは...」と不安に思いつつ依存症というレベルではないからと誰にも相談できずに困っている方も多いです)。
あるいは「孤独になるよりは良いから...」と窮屈で自己否定的な人間関係の中に身を置いておられる方もいます。
しかしこれも精神的には孤立しています。
しかし癒しは、孤立の上には達成しません。
人は人でしか癒されないからです。
当ルームは、こうした問題を抱える方の居場所です。
抑えこんでいた自分の気持ちに気づいて整理し、気持ちを否定せずにありのままに受け入れられることが、取り組みの第一歩です。
もちろんご自身のペースを大事にされて下さい。尻込みする気持ちや焦る気持ちとの取り組み方も含めてサポート致します。
2019/10/29
うつ病、適応障害、復職支援

うつ病の症状の代表的なものとして、
「罪悪感、自責感、焦燥感」があります。
休職し、まわりに迷惑をかけてしまっていると感じている方も多いのではないでしょうか?
しかし、その思考自体がうつの代表的な症状なのです。
そのため、同僚や家族から、「迷惑だなんて思ってないよ。大丈夫」と慰めても、気持ちが晴れることがありません。
場合によっては、「こんなに周りに気をつかわせるなんて、やっぱり自分はダメだ」と考え、ますます気分が落ち込むかもしれません。
家族としても、何と声をかけたら良いか分からないかもしれません。
「うつ病でがんばれは禁句なんですよね?じゃあ、どう声をかけたら良いのでしょう...」
ご家族からこんなご相談を受けることもあります。
うつの症状は、これまで築いてきた人間関係に大きな影響を与えます。
また、うつを発症させやすい人間関係やコミュニケーションのパターンもあり、悪循環から治りにくくなったり、再発につながりやすいのです。
当ルームでは、うつ症状、抑うつ状態、適応障害に苦しんでいる方のご相談をお受けしています。
また、うつを患う方のご家族のご相談もお受けしています。
2019/10/29
誤解されやすい人のカウンセリング

当ルームでは、
人から「誤解されやすい人」や
「誤解を受けて傷ついてきた人」に対してカウンセリングを行い、
こういった傷つき、生きづらさを抱える方の居場所として機能し、
生きやすくなるための道を共に模索しています。
「誤解されやすい人」の特徴や改善案はネット上に溢れています。
例えば、
「コミュニケーションが不足している。ちゃんと言葉化して、コミュニケーションを取りましょう」
「感情を表に出しましょう」
「愛想、愛嬌を振りまきましょう」
といったものです。
つまり
「人と積極的に関わって自己主張しましょう」がベースになった考え方です。
しかし、
『それができたら苦労しないわ!出来ないから困ってるんだ!!』
と思いませんか?
私なら思ってしまいます...
「誤解されやすい人」の特徴や改善案を知っていても実践につながりにくいのは、
誤解されてきた人の多くが
誤解を受けて傷ついたトラウマを抱えているためです。
例えば
・存在否定されるような発言、態度
・自己主張を抑えられた体験や自己主張は悪いものという刷りこみ
・「出る杭は打たれる」「目立つのは悪いこと」「分相応であれ」といった個人の足を引っ張る日本的な集団圧力
・パワハラ、いじめ
などです。
こういったトラウマが自己主張を妨げ、自己主張がないためますます誤解されるという悪循環を引き起こします。
そして、
・自己肯定感の低下
・職場で正当な評価が得られない
・嫌なことを押し付けられる
・孤独感
・親密な人間関係を築けない
・うつ病、適応障害など精神疾患の発症
・職を転々とする
といった問題に発展しやすくなります。
当ルームは、こういった問題を抱える方の居場所です。
自己一致して、自分を生かせる道を一緒に模索していきましょう。
2019/03/03
HSP (とても敏感過ぎる人々)

ここ数年で「私、HSP かもしれないです...」
という相談が増えています。
HSP とは、highly sensitive person (とても敏感過ぎる人々)の略です。
元々は、アメリカのユング派心理療法家エレイン・N ・ アーロン(Eleine N Alone)博士の研究によって提唱されたものです。
アーロン博士自身が自分の敏感過ぎる気質に悩んでおり、その後、心理療法家になり、似たような生きづらさを抱えているクライエントに多く出会ったことから、HSP 研究と概念につながりました。
敏感さは多岐に渡りますが、大きく分けると以下の4つに大別されます。
1)処理の深さ(Depth of processing)
感覚的な刺激を強く、深く、受けとり、処理する傾向があります。物事を深く掘り下げて考える性質があるため、子供の頃から、他の子があまり疑問に感じないようなことも考えていたという方が多いのです。
2)刺激の受けとりやすさ(overstimulated)
あらゆる刺激をキャッチしやすいのです。そのため、自分にとって不要で疲れる刺激や、多くの人が気に留めないような刺激も受け取ってしまいます。例えば、賑やかな場所が苦手だったり、人間関係のギスギスした雰囲気に人一倍敏感で、疲れやすかったりします。
3)情緒的な反応と高い共感性(Emotional reactivity and high Empathy )
情緒的な感受性が強く、感動しやすかったり、動揺しやすかったりなど、ポジティブ、ネガティブ両面で強く反応が出やすいです。
他者の気持ちにも敏感で、同情や共感といった形で、相手の気持ちに入り込みやすいです。
こうした資質をプラスに働かせ、芸術的素養を身に付けたり、対人援助職として活躍されている方もいます。
しかし、マイナスの側面として出ると、対人関係でトラブルに巻き込まれたり、巻き込んだりする可能性もあります。
4)些細な刺激に対する感受性(Sensitivity to Subtle stimuli)
刺激に対する五感の感度が非常に高いのです。音や匂い、身体の感覚に敏感です。そのため、例えば、服のタグのチクチク感が気になって落ち着かない、多くの人が気にならないような音や匂いに敏感で、具合が悪くなるといった方がいます。
こうした生きづらさを抱えていますが、
なかなか理解されず、
また、自分でも自分のことを理解しきれず、
苦しんでいる方が多いのです。
例えば、対人関係や他者の心の機微に敏感なのを
「気にし過ぎだね!スルースキルを身につければ?」
と言われてしまったり、
賑やかな場所が苦手などの過敏さを
「わがまま」、「社交性に欠ける」
と捉えられたり、
自分でも「まわりに迷惑をかけている」
と捉えやすい方も多いようです。
こうした特性は生まれ持った気質です。
研究の成果として、脳の扁桃体の反応しやすさが影響していると言われています。
にもかかわらず、
子供の頃から「直す」ように求められたり、
自分でも「自分はどこかおかしいのだろうか...」と悩んでいる場合もあります。
こうした生来の敏感な特性に、
周囲との齟齬が加わると、
うつ病やPTSD などの疾患にもつながりやすいことが知られています。
家庭環境や学校環境の中でのネガティブな刺激も敏感に受け取ってしまうため、非HSP に比べ、HSP はトラウマティックな体験に繋がりやすいことも指摘されています。
疾患までいかなくても、
慢性的な抑うつ状態、
自己肯定感の低さ、
トラウマ的な傷つき体験、
孤独感を抱えている方も多いのです。
精神的な問題だけでなく、
慢性的な疲労感や慢性疾患、
アトピーなどの皮膚疾患との関連も指摘されています。
(肌は外界と内界を隔てる境界線です。刺激が入り込みやすく、境界線を作るのが苦手なHSP らしい疾患と言えます)
HSP 特性は生まれ持った気質なので、「直す」ことではなく、自分を知り、受け入れ、活かすことが生きやすさの鍵です。
加えて、これまでの傷つきを癒し、自己肯定感を培っていくことも重要です。
また、HSP だからといって、まったく刺激がない状態が良いわけでもありません。
人は誰しも成長する上で適度な刺激を必要としています。
当ルームでは、様々な心理学的知見に基づいて、生きづらさを強みに変えるお手伝いをしています。